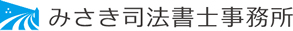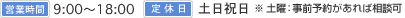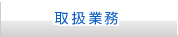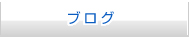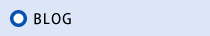2014.09.08.
その他【閉鎖謄本の取得代行】
最近、「謄本を代行で取得してもらえませんか?」というお問い合わせをよくいただきます
主な業務ではありませんので、特別に取扱業務や料金一覧にはメニューとして載せておりませんが、
実はよくあるご依頼だったりするのです。裏メニューですね。
とはいえ、謄本を取るだけなら誰にでもできますよね。
今はオンライン化されていて、どこの法務局でも全国の土地建物・法人の謄本も取ることができます。
ところが、オンライン化前の謄本については(オンラインと比較してブック謄本と呼ばれます。)、
管轄の法務局でしか保管されていないため、昔の土地・建物・法人の情報が知りたい場合には、
管轄の法務局まで行かないと、閲覧謄写をすることができないのです。
ですので、遠くに住んでいる方なら、現地に赴くのも大変ですし、
取得代行にもそれなりの意味があるんですね。
費用は実費と手数料です。
手数料は行く先の法務局までの距離、取得する通数などにより応相談です。
大阪府下の閉鎖謄本取得なら、みさき司法書士事務所にお任せください。
<みさき司法書士事務所>
2014.09.02.
相続【相続放棄と死亡保険金(共済金)の受領】
久しぶりに勉強になった小ネタを書きたいと思います
相続放棄、相続の限定承認をするまでの間に、亡くなった方の
相続財産を処分してしまっていた場合には相続を承認したものとみなされ、
相続放棄や相続の限定承認をすることができなくなってしまいます。
皆さんもどこかで聞かれたことがあるかもしれませんが、
「死亡保険金」は、受取人となっている方の固有の財産ですから相続財産ではありません。
したがって、相続放棄・相続の限定承認を予定している場合であっても、
死亡保険金だけは受け取ることができます
ところが、これが一般的な生命保険会社ではなく、共済の場合には気を付けないといけません
共済の場合、加入する際に出資した出資金の払い戻しも伴うことになります。
この出資金の法的性質は、相続財産ですから、うっかり払い戻しを受けてしまい、
相続財産を処分したと言われてしまっては困ります。
そこで、ある共済に確認したのですが、
このような場合、
「相続放棄を行うため、死亡共済金の受領だけを希望します。」
という内容の文章を書いて、住所氏名と実印での捺印があれば、
死亡共済金の受領だけに対応してくれるそうです。
相続の限定承認を行う場合には、
同様の手続きを行い、死亡共済金の受領だけをした後に、
出資金やその他の還付金については相続財産として計上する必要があります。
<みさき司法書士事務所>
2014.08.27.
その他【司法書士の出張相談について】
みさき司法書士事務所は、割と遠方の方のご依頼が多いです。
例えば、
南は沖縄、宮崎、熊本から、北は東京まで(それ以北はなぜかない。)。
遠方からのご依頼というのは、どうしても大阪の司法書士に依頼したい理由があるんです。
多くの場合が裁判所の管轄が大阪というような場合です。
もちろん、全くお会いしたことのない方のご依頼を受けるのは、
本人確認の問題もあって私は消極的なのですが、
なにかのついでに大阪へお越しいただいた際に面会したり、
住民票の所在地へ本人限定受取郵便で書類をお送りするなど、
できる限りの対応はさせていただいております。
(もちろん、本人確認書類のコピーもいただいています。)
これくらい大阪から遠い場合はこちらからの出張というのはほぼありませんが、
(もしろ、交通費出してもらえるなら喜んで行きます(笑))
逆に、大阪近郊の郊外の方から、出張相談に来てほしいとご依頼をいただくことはよくあります。
先日も少し遠くまで出張させていただいた際に、
「どうして近くの司法書士ではなく、私にご依頼いただいたのですか?」とお尋ねしたところ、
「近くの司法書士事務所に問い合わせてみたけど、
出張してないから事務所に来てくれって言われたんです。
それで、出張してくれる事務所をインターネットで探したんです。」
とのこと。
出張相談ができないって、あまりに不親切ではありませんか。
来てほしいと言われるからには、何か理由があるんです。
この方も、高齢で自宅からは出にくいという理由がありましたので、
私が訪問したことで大変喜んでいただけました。
また、遠方過ぎて費用対効果の面で、
私がご依頼を受けるより、現地の司法書士に依頼した方がよいと判断した場合、
全国青年司法書士協議会に所属している私には、全国各地に司法書士の友人がおりますので、
その方をご紹介させていただいております。
安心して任せることができる方ばかりです。
遠方のご依頼でも、これからもできる限りのご対応をしていきたいと思います。
遠慮なく、一度ご相談くださいね。
<みさき司法書士事務所>
2014.08.20.
不動産登記【住居表示の変更証明書】
ときどき、引っ越ししていないのに、「役所の都合で住所が変わってました」
ということがあります(住居表示の実施といいます。)。
不動産登記簿には、所有者の「住所」と「氏名」が記載されているのですが、
この役所の勝手な住所表示の変更によって、「住所」が変わってしまった場合でも、
登記簿上の住所の表記を現在の住所にするためには、
自分で変更の登記申請をする必要があります。
(登記にかかる登録免許税は非課税です。)
通常、住所変更の登記を申請する場合には、
住所に変更があった旨の証明書を添付しなければなりません。
この証明書は、変更の理由が引っ越しである場合には、
前住所からの沿革のわかる住民票を添付することになるのですが、
住居表示の場合には、住居表示があったことの証明書を添付しなければなりません。
この住居表示があったことの証明書は、
市役所の市民課で無料で発行してもらえます。
とくに申請書のひな形はありませんが(窓口まで行けば置いてあるようです。)、
私は次のような申請書を作って、役所に提出しています。
○○市役所 市民課 御中
下記の通り、住居表示があったことの証明書を1通交付願います。
記
①該当者の氏名
②旧住所
③新住所
④提出先
以上
大阪市北区西天満5丁目14番7号和光ビル8階
みさき司法書士事務所
司法書士 三輪 紗季子 ㊞
郵送の場合は返信用封筒を1通同封しておけば、返信してくれます。
代理人が申請する場合でも委任状等は必要なく、誰でも取得することができます。
詳しくは各市役所等の窓口に問い合わせれば、
親切に教えてもらえますよ。
<みさき司法書士事務所>
2014.08.15.
不動産登記【法人が事前通知を利用する場合】
事前通知というのは、登記義務者が権利証を失くした場合に、
義務者の登記簿上の住所地に、本人限定受け取り郵便にて、
「次のような登記申請がありましたが、間違っておりませんか?
間違っていなければ、実印で捺印して法務局に返送してくださいね~。」
というような通知が届く制度です。
この事前通知を省略するためには、司法書士が作成した
本人確認情報(本人確認した旨を記載して、司法書士が職印で捺印します。)を添付する必要があります。
不動産売買や、金融機関の抵当権の設定などの場合には、
義務者が事前通知に返信しないと、登記ができないというリスクを負うことになりますので、
ほぼ100%、司法書士が本人確認情報を作ることによって、事前通知を省略しています。
ただ、この本人確認情報を作成すると、どこの事務所でも高いんですよね~。
それは仕方がありません。
司法書士だって、初めてお会いする人が本人に間違いない旨を記載して、
職印で捺印するんですから、かなりのリスクを負うことになります。
もし、その人が本人でなかったら??と思うとゾッとしますね
なりすましの可能性も0ではないため、司法書士は責任が重大なのです。
権利証を失くさないでもらえたら一番良いんですけどね
みさき司法書士事務所では、依頼者のコストをできる限り下げるため、
権利証を紛失された方には、前述の通り、売買や抵当権設定でない限り、
事前通知制度の利用をお勧めしております
前置きが長くなりましたが、
義務者が法人の場合にはどこに事前通知が送付されるのか?
法人の場合は、事前に申し出ることによって
本店所在地ではなく、代表者の住所地に事前通知を送付してもらうことが可能です。
(具体的には、申請書に「代表者の住所地に送ってください」と記載しておきます。)
大きな会社の社長さんであれば、常に会社の本店に出勤しているわけではありませんので、
自宅に送付してもらえるのはありがたいですね。
<みさき司法書士事務所>