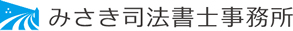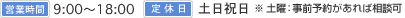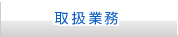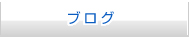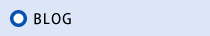2014.04.11.
不動産登記【代物弁済の登記と税金】
最近、次のような事案の登記の相談がありました
「Aさんの土地建物にAさんを債務者とする抵当権が設定されています。
抵当権の被担保債権は、実際にはAの息子であるBが返済していました。
BさんはA名義の不動産を、自分の名義にしたいけれど、どうしたらいいか?」
という相談です。
不動産の名義を変更するには、なんらかの物権変動の事由が必要です
「相続」だったり、「売買」だったり、「贈与」だったり…ですね。
AからBへの「贈与」とすると、Bに贈与税がかかってしまいます
(親子なので、相続時精算課税制度を利用する方法もありましたが、
過去に既にめいっぱい制度を利用しているので、今回は使えないとのこと。)
AからBへの「売買」とすると、実際にお金の流れがない以上は司法書士も登記ができませんし、
後から税務署に贈与と認定されてしまうとやっかいです
そこで、前述の事情があるのであれば、「代物弁済」で登記してはどうか?
という話になりました。
代物弁済というのは、「お金を借りた返済として、お金に代えて、物で返済する」という意味です。
ですから、今回であればAがBに立替金の返済として不動産で返済するということになります。
Bさんも被担保債権の返済は、贈与のつもりではなく、
立て替えて払っていたとの認識だったようですので、
代物弁済で登記して問題がなさそうです。
ところで、代物弁済で登記したときに、税務面では何か課税されるの!?と
税の専門家でない私にとっては大変不安でした
そこで調べてみましたら、なんと、今回の場合はAに譲渡所得税が課税される恐れがあるとのこと
税金のことを知らずに不動産の名義を動かすと恐ろしいことになりますね
代物弁済の登記についてはコチラ
<みさき司法書士事務所>
2014.04.09.
その他【死後事務委任契約と民法653条の強行法規性について】
最近は、なぜか一般の方よりも司法書士さんや税理士さんから、
「ブログ見てるよ」なんて言われることがあり、嬉しいような恥ずかしいような
書く内容にも気を遣わないとなぁなんて、思っています。
最近、知り合いから死後事務委任契約が民法653条(委任者の死亡による委任の終了)の条文との関係で
どちらが優先するの?と質問されました。
そもそも民法653条は強行法規なのか?
当事者の合意があれば民法の例外として、契約は有効なのか?という質問です。
これについて、いくつか判例があります。
最判平成4.9.22(原審:高松高判平成3.8.29)
委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払い、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払い、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払いを依頼する委任契約は、当然委任者の死亡によっても
契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものであり、民法653条の法意は右合意の効力を否定するものではない。
その他に、
東京高判平成11.12.21(原審:前橋地裁高崎支部平成10.10.21)
東京高判平成21.12.21(原審:東京地裁平成21.4.22)
いずれのケースにおいても、判例は民法653条の趣旨は任意規定であると解釈されているようです。
もともと、日本の民法典はドイツ民法典の影響を大きくうけ、その流れを汲んでいます。
ドイツ民法には、受任者の死亡により委任が終了する規定はありますが、
委任者の死亡による契約終了について、規定がないようです。
いずれにしましても、本人の死亡後に死後事務を行ったことで相続人と争うことになれば、
亡くなった本人も浮かばれませんよね
死後事務委任契約(任意後見契約も同様です)の際には、親族や推定相続人に集まってもらい、
本人と、受任者と、相続人との間できちんと話し合いをした上で契約を行うことが
トラブル防止のため、また、死後事務を円滑に行うために有効であると私は考えます。
委任事務の執行は、委任者の相続人の利益と衝突する可能性があるからです。
(本人から、「この人に死後事務をお願いすることにしたから。」との一言があるだけで、全然違いますから。)
特に死後事務を依頼する方はある程度高齢である場合が多いので、
いくら本人に判断能力があっても、親族が契約を知らなかった場合には、
後からトラブルになりやすいと思います
そして、契約はできれば公正証書で行う方が良いですね。
別に契約の効力発生要件ではないのですが、
公正証書で結んでおいた方が、契約書が真正に作られたという事実が担保されるからです。
だらだら書いていたら長くなってしまいました。
長いブログは読みにくいのでダメですね。
あぁ…でもこの分野はもっともっと書くべきことがたくさんあるので、また次回。
<みさき司法書士事務所>
2014.04.02.
相続【保険を利用した遺産相続】
こんにちは
今日もいい天気ですね~
最近
「私にはうつ病で働けず、自分で金銭管理させるには不安なひとり息子がいます。
自分の死亡後に財産を一度に相続させるとお金を一気に使ってしまい、生活できなくなる恐れがあるので、
すこしずつ相続させたいんだけど、そんな方法ありますか?」という相談を受けました。
それなら息子さんに補助人か保佐人を選任するべく、
お母さんから申立を行うとよいのでは…?と普通に考えたら思うんですが、
権利の制限を受けるのは嫌だということなんですよね。。。。
というわけで、信託銀行に信託するしかないんちゃいますか?
と思ったんですが、いかんせん銀行の信託報酬がお高い
信託しか方法がないのか?と思っていろいろ調べてみましたら、
死亡保険の一時払いで、契約者死亡後に相続人が年金形式で受け取れる…というのがありました。
けっこういろんな保険会社で同じような商品を取り扱っているみたいです。
(ただし、受け取りの手続きの際に年金形式で受け取るという欄に
☑を入れる必要があるみたいなので、それだけが気がかりですが…。)
あまり保険のことは詳しくないので、今回は私も大変勉強になりました
ご相談者様にも大変喜んでいただき、本当に良かったです。
なお、信託の場合は、受け取り方法を一時払いとするか年金形式で分配するかの選択は、
契約の時点で固定できるようですので、そういう意味では信託の方が契約者の契約の趣旨に沿った
活用ができかと思います。信託報酬を気にしないのであればですが。
親が子供に財産を残したいけれども、いっきに相続させるのは心配…
このような相談は今後は増えてくるかもしれませんね。
<みさき司法書士事務所>
2014.04.01.
その他【今日から4月!】
おはようございます。
バタバタしていた3月も終わり、今日から4月ですね!
今日は朝から設立登記の申請を行いました。
2週間以上前から、今日が設立の日と決まっていましたので、
絶対に間違いのないよう、気合を入れて申請しました。
(法人は登記申請日が設立日となりますので、みなさん縁起のいい日や、
何かの記念日に設立される方が多いんです
今日はなんだろう?仏滅やけど…エイプリルフール?)
世間では4月というと年度の始まりなので、心機一転という感じでしょうか?
私はといいますと、司法書士業務としてはあまり心機一転という感じはしないのですが、
来週からまた専門学校の前期授業がスタートし、新しい生徒との1年間が始まるという意味では、
4月は始まりの季節です
昨年は不動産取引の授業も担当しておりましたが、
今年は民法と会社法だけに減らしてもらいました
そのため、平日はゆっくり仕事ができるので気持ちに余裕ができました
とはいえ、今年は大阪司法書士会北支部の理事も内定しておりますし、
昨年度に引き続き、全国青年司法書士協議会の幹事もする予定ですので、
一年通してがっつりと仕事もプライベートも司法書士に関わっていくことになりそうです。
<みさき司法書士事務所>
2014.03.24.
その他【消費税と印紙税が4月1日から変わります。】
ついに4月1日から消費税が増税になりますね!
昨年は年度が切り替わる際、登記申請をオンライン申請で行った場合の
登録免許税の軽減措置がなくなるなどの変更がありましたが、
今年度は登録免許税に関しては、変更事項はありません。
変更になることと言えば、消費税くらいですかね
司法書士費用にも消費税をいただいておりますので、少し値上がりします
ごめんなさい
司法書士業務に絡んで、もう一つ改正が気になるのは、印紙税です
平成26年4月1日以降、一部の印紙税が引き下げられます。
以下に記載しますので、ご確認ください。
①領収証等の金額が5万円未満なら非課税になります。
領収証等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は、
現在は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、
平成26年4月1日以降は、非課税範囲が拡大され、
記載金額が5万円未満までが非課税になります。
(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです。)
②「不動産譲渡契約書」、「請負契約書」の印紙税が軽減されます。
| 契約金額 | 印紙税額 | |||
| 不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | 本則 | ~H26.3.31 | H26.4.1~H30.3.31 |
| 10万円超~50万円以下 | 100万円超~200万円以下 | 400円 | 400円 | 200円 |
| 50万円超~100万円以下 | 200万円超~300万円以下 | 1000円 | 1000円 | 500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 300万円超~500万円以下 | 2000円 | 2000円 | 1000円 |
| 500万円超~1000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 5000円 | |
| 1000万円超~5000万円以下 | 2万円 | 1万5000円 | 1万円 | |
| 5000万円超~1億円以下 | 6万円 | 4万5000円 | 3万円 | |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 8万円 | 6万円 | |
| 5億円超~10億円以下 | 20万円 | 18万円 | 16万円 | |
| 10億円超~50億円以下 | 40万円 | 36万円 | 32万円 | |
| 50億円超 | 60万円 | 54万円 | 48万円 | |
以上のようにすこ~しですが安くなります。
法律と判例と税金は、常に新しい情報を仕入れておく必要がありますね!
<みさき司法書士事務所>