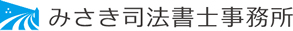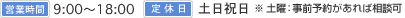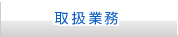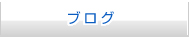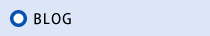2015.11.15.
司法書士【過疎地相談at大阪2015】
今日は大阪青年司法書士会主催、近畿司法書士会連合会共催で、
過疎地相談会を河南町と千早赤阪村において開催しました。
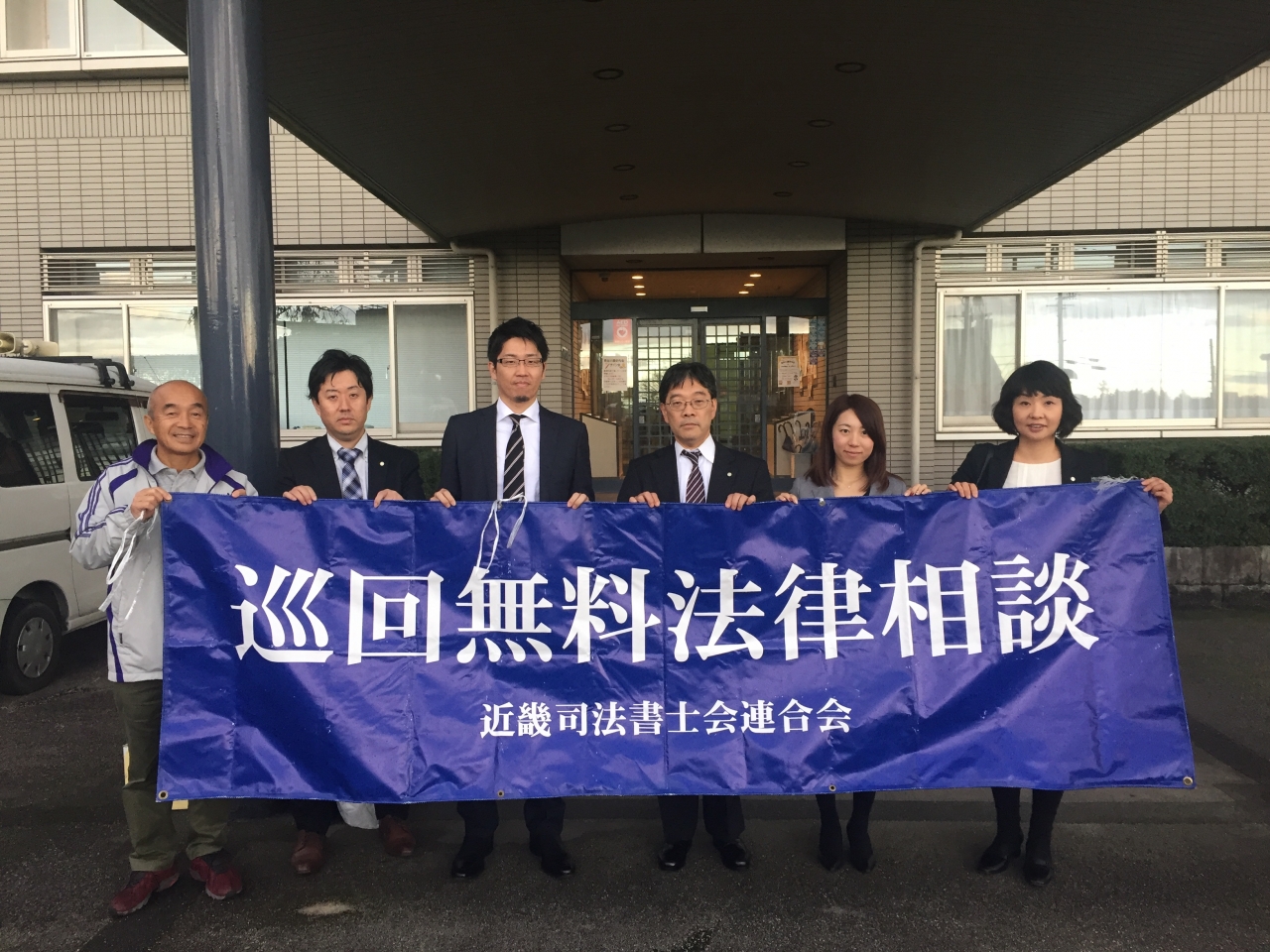
事前の広報活動にも毎年力を入れているのですが、相談件数は多くなく、残念でした。
(悩みがないというのは良いことかもしれませんが )
)
<みさき司法書士事務所>
2015.11.06.
相続【住所の沿革と上申書】
先日、住民票の除票の保管期限が短いため、困るという話をここに書いたと思います。
(詳しくはコチラ)
どうして困るかと言いますと、
相続登記の申請の際、被相続人の最後の住所地と、登記簿上の住所地の沿革をつけるため、
住民票の除票(本籍省略無)又は戸籍の附票を添付する必要があります
(これにより、死亡した者と登記簿上の人物が同一人物であることを立証します。)
この際に、住民票の除票や戸籍の附票が保管期限の経過により取得できない場合、
上申書を添付する必要があるからです。
この上申書は法定添付書面ではありませんので、ご当地ルールがあるようです…。
私は毎回、相続人全員から捺印をもらっていたのですが、先日疑問に思って登記官に聞いたら
大阪法務局管内(おそらく近畿圏内は同様の取扱いだと思われます。)では、次の取り扱いになっていると教えてくれました。
第一に、
相続により名義を取得する人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+被相続人の権利証
権利証が紛失してしまって存在しない場合は、
第二に、
相続人全員からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+固定資産税の納税通知書+固定資産税の領収書
納税通知書もない場合は、
第三に、
相続人全員からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+成人2名による保証書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)
だそうです。
今まで全くそんなルールを意識しておりませんでしたので、驚きました
このルールさえも地域性があると言われると、結局毎回法務局に確認しないと不安ですね
<みさき司法書士事務所>
2015.11.02.
相続【住民票の添付が不可能な場合】

今日から11月で、今年も残すところあと2ヶ月となりました

事務所も開業して3年が経ちましたが、3年前のこの時期より、今忙しいのはありがたいことです

今日も最近思い出した先例を備忘録としてここに書きます。
シチュエーションとしてはかなりレアなのですが、
相続登記の申請の際に、行方不明だったり、既に死亡して5年以上が経過しており、
住民票が出てこない者が共同相続人の中に存在する場合があります。
そんな中、遺産分割ができず、どうしてもいったん共同相続人全員の名前で登記しないといけないような場合に
(↑シチュエーションが限定的すぎ
 )、
)、住民票が出せない人は、どうやって登記すれば良いのか…?
結論から言うと、さしあたり本籍地を住所として登記することになります。
【先例】
過去に数次相続が発生しており、遺産分割ができずにとりあえず法定相続分で登記を入れようとしたところ、
共同相続人の中に死亡して5年以上経過しており、住民票の除票すら出てこなかった者があり、
1回だけこの方法で登記を行いました。
住民票の除票が5年で廃棄されるという仕組みは本当に廃止になってほしいです。
永久保存ではどうしていけないのでしょう?

(現在、司法書士政治連盟がこの問題について、議員立法を目指して動いているという話は聞いたことがありますが…。)
住民票の除票が廃棄されて困るケースについて、
また明日以降にブログを更新したいと思います。
<みさき司法書士事務所>
2015.10.22.
成年後見【遺産分割協議における成年後見人の利益相反】
成年後見人をしていて最近とても悩んだ事案があります
本人に、親族後見人と専門職後見人(私)の2人の成年後見人が選任されている事案で、
本人の父親に相続が発生し、遺産分割協議を行うことになりました。
遺産分割協議を行うにあたり、本人と、親族後見人の2名が相続人当事者になります。
この場合、専門職後見人(私)が本人を代理して、親族後見人との間で行った遺産分割協議は有効か否か
という問題です。
未成年者の場合、
親権者たる父母の一方に民法第826条第1項にいう利益相反関係があるときは、
利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである
(最判昭35.2.25)
という判例がありますから、一方とのみ利益が相反する場合であっても、特別代理人の選任を要します。
(特別代理人の選任の概要はコチラ)
では、
本人に成年後見人が2人いる場合(権限分掌なし。)において、
一方に利益相反があるときはその一方のために特別代理人を選任する必要があるのか…
と思い、家庭裁判所に上申書を出してみました。
すると、「特別代理人は選任せず、専門職後見人(私)が本人を代理して、親族後見人との間で遺産分割を行っていただいて結構です。」と言われました
あれ?そうなの?!と思って、その理由を考えてみました。
この違いは、民法上の条文に起因するのではないかと思われます。
未成年者の場合、
民法818条
1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
と規定されており、親権の場合は、父母が共同して行使する必要があります
これに対して、成年後見人の場合は、事務を共同して行使しないといけないという定めはありません
(なお、未成年後見人が複数人ある場合には、民法857条の2によれば、事務は共同して行使する必要があります。)
そのため、今回のケースでは特別代理人を選任する必要はないようです。
細かい話ですが、困ったときは条文に立ち戻って考えることは本当に大事ですね
<みさき司法書士事務所>
2015.10.15.
司法書士【H27年度司法書士試験・二次試験】
先日、平成27年度司法書士試験の二次試験(口述)が開催されました。
大阪での今年の一次試験通過者は47人とのこと。
私は二次試験の始まる8時~9時の間、
大阪法務局前で大阪青年司法書士会の新人さん勧誘のためのビラ配りをしていました。
(この時期の8時台って寒いですね~ )
)

司法書士の口述試験は、キツイですよね。
ただでさえ試験官の目の前で緊張して、頭が真っ白になってしまうというのに、
本試験終了後、一次試験の合格発表までの3ヶ月、気を抜いたら知識が頭から抜け落ちていくので、
記憶レベルを3ヶ月は維持しないといけないんです
そういえばもう遠い昔ですが、私が受験生だった頃、二次試験の受験会場で緊張しながら座っていたら、隣に座ったおっちゃんが話しかけてくれました。
私が「緊張しますよね~。」と話したところ、おっちゃんは、「大丈夫や。試験官だって法務局の職員やろ?年に1回の試験やし、あいつらも緊張してるやろ。お互い様や。」となんともたくましい発言。
それもそうだな~と思った経験がありました。
おっちゃんも合格しているはずなので、多分同期の司法書士のハズなんですが、今となってはあの時のおっちゃんが誰なのかわからないのが残念で仕方ありません。
<みさき司法書士事務所>