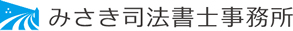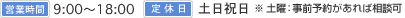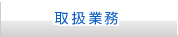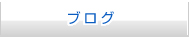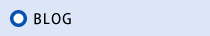2015.02.18.
相続【戸籍の職権訂正について】
最近、相続の依頼を受けて戸籍を集めておりましたところ、
「んっ?? 」
」
被相続人が配偶者と子供なく死亡したため、兄弟が相続人になるというケースなのですが、
取れた戸籍をよ~く見ると、兄弟のうち1人だけ、
父親欄の父親の名前が間違っていて、父親が他人になっている…
(字の間違いではなく、完全に他人の名前になっていました )
)
戸籍を最初から順番に辿っていけば、
父親が他の兄弟と同じであることは暗黙の了解でわかるのですが、
どうやら、本籍地を転籍して新たに戸籍を編製した際に、そのときの担当者が間違えたのでしょう。
現在の戸籍だけで見ると、半分しか血が繋がっていない兄弟のよう
昔は手書きだったし、人間のやることにミスはつきもの…。
とはいえ、戸籍ですから!!!
もう何十年も前の戸籍やし、訂正とかしてもらえるんかなぁ~。と思って
そこの市役所に事情を説明し、手元にある戸籍を見てもらいましたら、
「すみません。職権訂正します!」と言ってもらえました。
市役所の職権請求で転籍前の戸籍を取り寄せ、審議にかけてからの訂正になるため、
1週間から10日ほどかかるそうです。
その間仕事がはかどらない…
それにしても、気づいた私、ナイス。
<みさき司法書士事務所>
2015.02.09.
相続【地方裁判所の和解調書を添付した相続登記】
昨年末、弁護士さんからちょっと困った相談がありました。
地方裁判所で遺産分割を行った和解調書を添付して、
相続人から単独で相続登記申請ができるかどうかです。
民法の規定では、遺産分割が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求できるとなっており、
遺産分割は家庭裁判所で行うことが民法上要請されています。
したがって、通常、争いのある遺産分割協議は家庭裁判所で行うため、添付するとすれば、
家庭裁判所の調停調書、審判書正本、判決正本です。
ところが、遺産分割の前提問題(例えば本人死亡前後に使途不明金があるとか…。)がある場合には、
前提問題は家庭裁判所ではなく、別途地方裁判所や簡易裁判所で解決することになります。
今回のケースは、地方裁判所で前提問題を解決した上で、
遺産分割協議もついでに行ったので、その和解調書を添付して登記したいという相談でした。
そこで、この地方裁判所での和解調書を添付して単独での相続登記申請ができるのか?
という問題に発展しました。
地裁での和解調書の場合、家庭裁判所での遺産分割の調書と異なり、
必ずしも相続人全員が関与しているとは限らない点と、
民法上の要請があるため、判決と同じ効力を有すると言っても、
家庭裁判所での調停調書と全く同じように扱うというのは難しいかもしれません。
しかし、遺産分割の和解に相続人全員が参加しているということであれば、
戸籍謄本等を添付することにより、登記原因証明情報として利用することができると考えるのが自然です。
そのため、いろいろ調べたところ(同業者にも法務局にも確認しました。)、
■登記名義人(被相続人)の相続人全員が当事者となっている。
■和解調書には、被相続人名義の不動産を特定の相続人が取得する旨の遺産分割協議が和解成立と同日に成立したことを確認する条項がある。
この要件を満たせば、なんとか地方裁判所で行われた遺産分割協議の和解調書正本を添付して、
相続登記の申請ができるということがわかりました。
なお、相続人全員が参加している旨(相続人確定)の記載が調書から明らかでない場合は、
相続人を明らかにするため、戸籍謄本等は全て添付する必要があります。
実務上、家庭裁判所では、使途不明金等の前提問題で争っている場合は、
「別途地方裁判所で解決してから家裁に遺産分割を持ち込んでくださいね。」
という説明がされているそうですが、
きっと地方裁判所で主たる請求のついでに、遺産分割も和解でまとめてしまったんでしょう。
もう一度遺産分割協議書を作って相続人全員から実印押して印鑑証明書付けてもらって…
となると、相続人同士が揉めている事案ではお願いしにくいので、
和解調書正本の添付で登記ができることがわかり、安心しました。
地方裁判所で遺産分割ができてしまうのであれば、その方が手っ取り早いですよね。
実務上、よくあることなのかな?
<みさき司法書士事務所>
2015.02.02.
その他【本の出版】
年が明けたと思った瞬間、1月が終わってしまいました
月日が経つのは速いですね。
実は、一昨年からずっと介護関連の勉強会を仲の良い弁護士の先生たちと共同で行っており、
(具体的には介護関係に従事しているケアマネさんや社長さんをお招きして、
業界のお話をたくさん聞かせていただいていました。)
そのメンバーで去年から本の執筆をしていたのですが、その締切がこの1月末でした
直前になって変更する部分がたくさんあり、とにかく大変でした。
練って練って、何度も何度も変更や訂正を繰り返しながら書いた文章には愛着がわいてきます。
Q&A本なのですが、私が主に担当させていただいたのは、
・任意後見制度の概要
・死後事務委任契約の有効性と問題点
・医療行為の同意について
・後見制度支援信託の運用
・成年後見開始の審判申立権者
・成年後見人候補者について
・身寄りのない方が死亡した場合
の7つのQ&Aです。
出版予定が5月なので、まだこれから仕上がってくるゲラを著者校正していく段階です。
本がたくさん売れますように…
そして、たくさんの人に読んでもらって、参考にしていただけますように!!
また、本のタイトルや出版予定日が確実に決まり次第、
あらためてご報告させていただきます。
<みさき司法書士事務所>
2015.01.26.
商業登記【平成27年2月からの登記規則改正について】
平成27年2月27日から、商業登記規則の一部に改正があるそうです。
主な内容としては
①株式会社の設立登記又は取締役等の就任の登記申請の際に、今までいらなかった住民票等本人確認資料の添付を要すること。
(選任議事録や就任承諾書には役員の住所の記載が必須になります。)
②代表取締役等(法務局に印鑑を届け出ている者)の辞任届には、法務局届出印の押印又は実印の押印と印鑑証明書を要すること
③現在の氏とともに婚姻前の氏を登記簿に記録するよう申出ができること
だそうです。
①については、以前から(不動産登記に比べて)商業登記はザルだなぁ…
と思っておりましたので、もっともな改正なのではないかと思いました。
ちょうど2月18日に設立登記を予定しているので、いつから施行なのかハラハラしていました。
添付書類に変更があると、
改正前後はとまどいますね。
<みさき司法書士事務所>
2015.01.25.
相続【生前の相続放棄】
被相続人の生前に、相続人のうちの一人に対して、
「相続権を放棄します、と一筆書いておいてもらう」と話す方が多いような気がします。
しかし残念ながら、民法では被相続人の生前に相続放棄をすることは認められておりません。
(生前の遺留分の放棄は認められています。)
当然、生前の遺産分割も、何の意味もありません。
もし「相続を放棄します。」と被相続人の生前に一筆書いてもらった場合において、
将来いざ相続が発生したときに、「あのとき書いてもらったでしょ?」ということで
素直に遺産分割で相続権を他の相続人に譲ってくれれば良いのですが、
「気が変わったから自分も相続したい。」と言われてしまうとアウトです。
だってそもそも生前の相続放棄の約束や遺産分割の約束は無効ですから。
遺産分割が調わず調停や裁判となったとき、
昔書いてもらった書面を武器に、当該相続人には相続分は与えないと主張できるか?と言われると、
主張できません…。
ですので、無効なのは承知の上で、一応書いておいてもらうということであれば良いのですが、
本気で相続対策ができると思っている人は要注意です。
このような場合には、遺言が一番です。
とはいえ、遺言を書いた場合でも、兄弟が相続人となる場合以外には相続人は遺留分を有しますので、
遺留分相当の金員は与える内容の遺言を作成するか、生前贈与を行うことによって、
生前に遺留分の放棄をさせておくことが望ましいでしょう。
(遺留分についてはコチラ)
また、相続人が非行をしたことにより、相続排除をしたいということであれば、
被相続人の生前に家庭裁判所に申し立てて相続排除の手続きを行えば(遺言でも可能。)、
相続人たる地位を排除することもできます。
(ただし、かなりの非行をしていない限り、認められないため、ハードルは高いです。)
<みさき司法書士事務所>