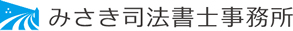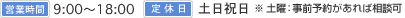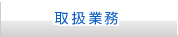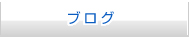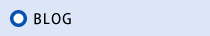2013.12.30.
その他【仕事納め】
今日で仕事納めです
今年も一年間、いろんな事件や登記に関わらせていただき、また一回り成長できた一年になりました。
本当にありがとうございます。
来年も更なる成長の一年になるよう、日々実務経験を磨いていきたいと思います。
皆様よい年末年始をお過ごしくださいね
<みさき司法書士事務所>
2013.12.27.
司法書士【年越し電話相談会】
25日に年越し電話相談会という電話相談会に2時間程度ですが、参加させていただきました
弁護士さんやその他関連団体と合同で行いました。
生活保護や多重債務問題に関することを中心とした相談でしたが、その他の相談も多く寄せられました。
NHKのお昼のニュースで流していただいたこともあってか、
最終62件の相談を受け付けたと聞いております。
年末は何かと急な相談も多いですよね
私の事務所もなぜか年末に限って駆け込みのような相談が増えています。
今年は一応30日まで営業する予定にしておりますので、
もし急な相談があれば、30日までなら対応させていただきます
<みさき司法書士事務所>
2013.12.24.
司法書士【クレアホール相談会】
21日に、布施にあるクレアホールで大阪司法書士会自死問題対策委員会が主催となって相談会を実施しました。
この相談会は少し特殊で、こころがしんどいな~と思う人を対象としたなんでも相談会です。
法律相談からこころの相談までを司法書士と臨床心理士が一緒になって行う、非常に特殊な相談会でした。
臨床心理士さんと合同で相談を受けるのは初めてだったのですが、
司法書士と違って、質問の仕方や話の聞き方も上手です。
(法律家はどうしても、話の結論を急いでしまう傾向にあるんですよね。。。)
すごく勉強になりました。
私は参加しませんが1月、2月にも合同相談会を実施する予定があります。
司法書士会としてもこのような取り組みに力を入れていくのはとても斬新で良いことですね
<みさき司法書士事務所>
2013.12.19.
相続【相続させる旨の遺言について】
遺言を書く際に、気を付けるべきなのは、その文言です。
多くの場合、遺言を書くときに思いつくのが「遺贈する」とか「贈与する」、「相続させる」などの言葉です。
いずれも遺言者の死亡により、ただちに受遺者に対して所有権移転の効果が生ずる点では同様です。
しかし、対象財産に不動産がある場合には、登記手続きの点において、
「相続させる」と記載する方が相続人にとって有利となることがあります。
判例では、
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定をなしたものと解すべきであり、当該遺産は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちに当該相続人に相続により承継される(最判平3.4.19)。
とあります。
これを受けて、不動産登記の手続きにおいては、
「遺贈する」と記載がある場合に、受遺者と全相続人(又は遺言執行者)との共同申請が必要であることに対して、
「相続させる」と記載がある場合には、受遺者から単独で申請することができることになります。
また、第三者に対する対抗要件の点では、
「遺贈する」と記載がある場合には、登記が対抗要件であることに対して、
「相続させる」と記載がある場合には、登記なくして第三者に対抗することができます。
以上の点から、遺言によってある特定の相続人に対して特定の財産を与えようとする場合、
「相続させる」との文言を用いた方がメリットの多いことがわかります。
このため、実務上はこの表現がもっぱら使用されています。
私も依頼を受けて遺言案を作成する際には、必ずこの表現を用います。
なお、相続人ではない人物に遺言で財産を残す場合には、「相続させる」との文言を用いたところで、
(遺言は無効ではありませんが)遺贈と同じ扱いを受けますので、前述のメリットはありません。
<みさき司法書士事務所>
2013.12.17.
不動産登記【相続放棄と相続登記】
相続の登記をする際に、相続人の中に相続放棄をしている者がいる場合は、
「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要があります。
この証明書なのですが、
相続放棄の申述が受理された際に家庭裁判所から発行される
「相続放棄申述受理通知書」なる書面と勘違いされている方が多いです。
通知書はあくまで裁判所からの「終わりましたよ~」というお知らせのようなものであって、
「証明書」ではありません。
「相続放棄申述受理証明書」は、別途、事件を扱った家庭裁判所に
証明申請書(150円の収入印紙が必要)を提出して、発行してもらう必要があります。
証明書は登記の申請以外にも、例えば被相続人の債権者がいる場合に、
「証明書を出してくれ!」と言われる場合もあります。
余談ですが、私の事務所では、相続放棄の依頼を受けた際は、通知書をもらって終わりではなく、
一応「証明書」も取得した上で、依頼者の方にお渡しするようにしております。。。
そして、この証明書は利害関係を証明して、利害関係人からも取得できますので、
相続放棄した本人からの協力が得られない場合でも、差し支えありません。
自分で取得できないという方は遠慮なくご相談くださいね
<みさき司法書士事務所>