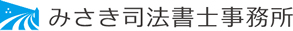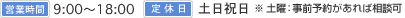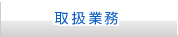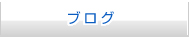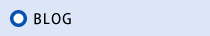2014.12.21.
その他【コミュニケーションの研修】
昨日は、NPO法人自死をなくす会コアセンター・コスモスさんが主催の
「コミュニケーション、話の聴き方」についての研修に参加してきました。
司法書士にとって、「話を聴く力」というのはとても大切なものです。
(人の話を聴くのが仕事みたいなものですから )
)
もちろん、人間関係を築く上でも、重要なものではないでしょうか。
コミュニケーションに関する研修はときどき受けるのですが、
技術的なことは学んでは忘れ、学んでは忘れ…なかなか勉強だけしても身につくものではありません。
技術はさておき、特に納得したことだけ、ここに書いて皆さんと共有したいと思います。
まず、コミュニケーションとは何か?ということについてですが、
英語では「common(共有)」と「union(1つになる)」がくっついてcommunicationとなります。
したがって、コミュニケーションとは、相手に伝え、相手から話を聴くことで、
事実・意見・感情を共有することだと考えることができます。
そして、コミュニケーションにはレベルがあるというお話がとてもしっくりときたのですが、
コミュニケーションは7段階に分けて考えることができます。
①スイッチオフの状態(ex.電車の中での他人との距離感)
②挨拶を交わす
③事実や出来事を共有する
④考えや意見を共有する
⑤肯定的な感情を共有する(ex.嬉しかったことなど)
⑥否定的な感情を共有する(ex.悲しかったことなど)
⑦無条件の愛
⑤~⑦の感情レベルでのコミュニケーションが足りないと、孤立する原因になるそうです。
上手なコミュニケーションをするには、まずは「聴く」ということが大切です。
「聞く(hear)」のではありません。「聴く(listen」です。
hearは聞こえてくる、listenは意識して聴くという意味です。
自分の話を聴いてくれていると相手が感じれば、相手はさらに深い話をしてくれるようになります。
このようにして、まずは相手の話を聴くこと。
それも、相手が話しやすいような環境を作ってやること(ここで初めてスキルの話になってきます。)。
スキルは何度勉強しても、普段の会話の中でなかなか意識して実践できないので、
会話の中で意識するとすれば、「感情を共有する」ことを目指すということでしょうか。
これを普段から意識して実践していけたらいいなぁと、そう思いました。
勉強になりました。
<みさき司法書士事務所>
2014.12.17.
相続【養子縁組前の子が代襲相続して相続人となる場合】
お久しぶりの更新です
最近へぇぇぇぇぇ~ と思った相続についての判例があります
と思った相続についての判例があります
民法では、養子縁組後の養子Aの実子Bは、養親Cの直系卑属にあたるため、
養子Aが先に死亡していた場合には、養親Cの相続について、Bは代襲相続人となります。
では、もしBがAとCの養子縁組前に生まれていたら??
答えは、「代襲して相続人となりません。」と答えますよね。
ところが、こんな判例がありました。
養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって、養親の直系卑属にあたる場合には、
養親を被相続人とする相続において、養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる。
(大阪高裁平元8.10判決)
(判例タイムズ708号222頁)
これってよくある話ですよね。
婿をもらって、奥さんの両親とお婿さんが養子縁組しているような場合や、
お嫁さんと、夫の両親が養子縁組しているような場合です。
(もっとわかりやすい例で言いますと、磯野家においてマ○オさんとナ○ヘイさんが縁組しているような。)
この場合に、夫婦間に生まれた子(つまり、タ○ちゃん)は、養子縁組より出生日が前であっても、後であっても、
養子(マ○オさん)の方が先に亡くなれば、養親(ナ○ヘイさん)の相続について、
子(タ○ちゃん)は養子を代襲して、相続人となるのです。
判旨は次の通りです。
『民法887条2項但書において、「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の範囲から排除した理由は、
血統継続の思想を尊重するとともに、親族共同体的な観点から相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、とくに単身養子の場合において、縁組前の養子の子が他で生活していて養親とはなんら関わりがないにも関わらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるからこれを排除する必要があったことによるものと考えられる』
ため、本件のような場合については代襲相続を認めるとしています。
今月で一番勉強になった判例です。
<みさき司法書士事務所>
2014.12.07.
相続【ジョイント口座の相続】
昨日は士業同士の勉強会を行い、大変興味深い判例を勉強しました。
ハワイ州で作成されたジョイント口座(共同名義口座)をめぐっての相続問題についての判例です。
そもそもジョイント口座という口座自体、私は知らなかったのですが、
ジョイント口座というのは、2名以上が共同で作った銀行口座のことで、
日本の金融機関ではジョイント口座は作れないのですが、海外ではよくあることなのだそうです。
ジョイント口座の共有者の1人に相続が発生した場合に、
その口座の中にあるお金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれるかどうか…というところで、
東京高裁平成26年11月20日判決では、
「ハワイ州のジョイント口座は被相続人の私法上の相続財産を構成しない」と判断した第一審判決を支持しました。
つまり、ジョイント口座に入っているお金は、相続財産に含まれないと判断したのです。
この銀行との契約では、預金口座は預金口座の所在地(ハワイ州)の法律により規律されるという定めがあったため、
ジョイント口座が相続の客体となりうるか否かはハワイ州法によって判断すべきであるとし、
ハワイ州の法律では、ジョイント口座は生存名義人に帰属させないとする意思の存在を裏付ける明確で客観的な証拠がない限り、生存名義人に帰属すると定められていることを指摘した上で、今回の事案では証拠がなかったため、相続財産を構成しないとの判断になったようです。
これ、ハワイ州の法律に従った結果の判断ですので、
銀行がハワイの銀行でなかったら、また違う結果になったのでしょうか
海外で口座を作る人が増えているので、
このような事案もこれからどんどん増えてくるのでしょうね…。
海外に財産を持つと、海外の法律が適用されることもあるため、複雑です
日ごろからしっかり勉強して、世の中の動きについていこうと思います!
<みさき司法書士事務所>
2014.12.06.
相続【一人遺産分割の可否について】
父親が亡くなり、母と息子だけが相続人であるようなケースにおいて、
その後に母が亡くなれば(数次相続)、息子が母親の地位を相続した者として父親の遺産分割協議を1人で行い、
息子名義に一発で変更することができるということは、慣習的に最近まで当たり前のように行われていました。
私も何度もやったことがあります。
ところが、平成26年3月13日東京地裁での判決(平成25年(行ウ)372号)で、この点に明確な判断がなされました。
一人遺産分割協議に基づいた登記申請が却下されたケースについて、
遺産分割は、複数の相続人の存在が当然の前提とされているため、
2次相続によって最終的に相続人が1人となった場合には、法律上遺産分割の余地がないことから、
法務局の却下決定を「適法だ」としたものです
この判例を受けて、
各地の法務局では同様の申請があった場合には、取下げを要求してくるようになっています。
本当につい最近(すくなくとも平成26年9月頃まで)までは当たり前にできていたことなので、驚きました。
これに基づけば、冒頭のようなケースでは、いったん亡母親と息子の共有名義に相続を原因として所有権移転登記をした後、亡母親持分について相続を原因として息子名義に所有権移転登記を行う…という2段階の申請が必要となります。
つまり、登録免許税が2倍かかるということです…
<みさき司法書士事務所>
2014.12.01.
成年後見【後見制度支援信託】
私のところにも、ついに後見制度支援信託を利用する事案の成年後見の依頼が、
家庭裁判所から回ってきました
後見制度支援信託とは、近年、親族後見人が本人の財産を横領するなどの不正行為が多発していることから、親族が成年後見人として職務を行うことに問題がないと見込まれる事案において、適切な財産管理・不正行為の防止を目的として、最高裁判所が導入する方針を示したもので、平成24年から各地の家庭裁判所で試験的に運用が始まっています
具体的には、家庭裁判所が後見制度支援信託の利用が相当であると判断した事案について、専門職後見人が選任され、その管理する被後見人の財産のうち、日常的に必要なお金を預金口座に残して残りは全て信託銀行に預け、親族後見人に財産管理を引き継ぐというものです。
当初、新規案件(これから審判が下りるもの)にしか利用されないと聞いていたのですが、
私のところへ来たのは、親族がこれまで管理を続けていたという継続案件でした。
家庭裁判所に世間話ついでに聞いてみたら、最近は増えてますとのこと。
裁判所の職権で成年後見人が選任され、強制的に信託されてしまうのですから、
今まできちんと財産管理を続けていた親族後見人からすれば、気の悪い話ですね。
とはいえ、成年後見制度は親族の誰かのためではなく、
あくまでも本人のための制度ですから、仕方のないことなのかもしれません。
<みさき司法書士事務所>